この記事では、「剰余の定理」についてわかりやすく解説していきます。
定理の証明や因数定理との違い、問題の解き方を紹介していくので、ぜひこの記事を通してマスターしてくださいね!
目次
剰余の定理とは?
剰余の定理とは、整式を一次式で割ったときの余りに関する定理です。
整式 \(P(x)\) を
- 一次式 \((x − a)\) で割ったときの余りは \(P(a)\)
- 一次式 \((ax + b)\) で割ったときの余りは \(\displaystyle P\left( −\frac{b}{a} \right)\)
である。
商の一次式が \(0\) となるような \(x\) を \(P(x)\) に代入した値が余りになるということですね。
剰余の定理を利用すると、整式をわざわざ割り算しないですぐに余りを求められます。
剰余の定理の証明
剰余の定理がなぜ成り立つのか、証明していきます。
整式 \(P(x)\) を一次式 \((ax + b)\) で割ったときの余りは \(\displaystyle P \left( −\frac{b}{a} \right)\) となることを証明せよ。
商と余りを文字でおいて式を立ててみると確認できます。
整式 \(P(x)\) を一次式 \((ax + b)\) で割ったときの商を \(Q(x)\)、余りを \(R\) とおくと、
\(P(x) = (ax + b)Q(x) + R\) …①
と表せる。
ここで、①に \(\displaystyle x = −\frac{b}{a}\) を代入すると、
\(\displaystyle P \left( −\frac{b}{a} \right)\)
\(\displaystyle = \left\{a \cdot \left( −\frac{b}{a} \right) + b \right\} Q\left( −\frac{b}{a} \right) + R\)
\(\displaystyle = (−b + b) Q\left( −\frac{b}{a} \right) + R\)
\(\displaystyle = 0 \cdot Q\left( −\frac{b}{a} \right) + R\)
\(= R\)
\(\displaystyle R = P \left( −\frac{b}{a} \right)\) より、剰余の定理が成り立つ。
(証明終わり)
このように、余りが \(\displaystyle P \left( −\frac{b}{a} \right)\) と等しくなることがわかりましたね。
商や余りを文字でおいて計算を進める手法は実際の問題でもよく使うので、見慣れておきましょう!
剰余の定理と因数定理の違い
ここでは、剰余の定理と因数定理の違いを説明します。
実は、「剰余の定理」において余りが \(0\) のとき、つまり整式が割り切れるときが「因数定理」なのです。
- 剰余の定理
整式 \(P(x)\) を一次式 \((x − a)\) で割ったときの余りは \(P(a)\) である。 - 因数定理
整式 \(P(x)\) が一次式 \((x − a)\) を因数にもつ \(\Longleftrightarrow\) \(P(a) = 0\)
余りが \(0\) ということは、\((x − a)\) で割ったときの商を \(Q(x)\) とおくと
\(P(x) = (x − a) Q(x) + 0\)
\(x = a\) を代入すると、
\(\begin{align} P(a) &= (a − a) Q(x) + 0 \\ &= 0 \end{align}\)
となり、因数定理「整式 \(P(x)\) が \((x − a)\) を因数にもつ \(\Longleftrightarrow\) \(P(a) = 0\)」が成り立つのです。
つまり、因数定理は特別な条件下(= 整式が一次式で割り切れる場合)における剰余の定理といえますね。
剰余の定理の使い方
例題を通して、剰余の定理の使い方を説明します。
例題①「整式の割り算の余りを求める」
整式 \(P(x) = 3x^2 + 2x + 1\) を \((x + 1)\) で割った余りを求めよ。
整式を一次式で割った余りに関する問題なので、剰余の定理が使えます。
剰余の定理を使うと、素直に整式を割り算するよりも楽に余りが求められます。
剰余の定理より、\(P(x)\) を \((x + 1)\) で割った余りは \(P(−1)\)
\(x = −1\) を \(P(x)\) に代入して
\(\begin{align}P(−1) &= 3 \cdot (−1)^2 + 2 \cdot (−1) + 1 \\&= 3 − 2 + 1 \\&= 2\end{align}\)
答え: \(\color{red}{2}\)
例題②「商と余りから定数を求める」
整式 \(P(x) = 2x^3 + ax^2 − bx + 1\) は、\((x − 1)\) で割ると \(3\) 余り、\((x + 1)\) で割ると \(5\) 余る。
このとき、\(a\), \(b\) の値をそれぞれ求めなさい。
「〜で割ると〜余る」という表現が出てきたら、即「剰余の定理だ!」と思ってください。
問題文から関係式が \(2\) つ立てられるので、その \(2\) 式を連立して \(a\), \(b\) を求めます。
まずは問題文の「\((x − 1)\) で割ると \(3\) 余り、\((x + 1)\) で割ると \(5\) 余る」の部分を剰余の定理で数式として表します。
ここでは、特に計算は必要ありません。
\(P(x) = 2x^3 + ax^2 − bx + 1\) において、剰余の定理より
\(P(1) = 3\), \(P(−1) = 5\)
問題の整式に \(x = 1\), \(x = −1\) を代入して、\(P(1)\), \(P(−1)\) を表します。
これが STEP.1 の式と等しいことから、定数 \(a\), \(b\) の関係式を \(2\) つ得ます。
\(\begin{align} P(1) &= 2 \cdot 1^3 + a \cdot 1^2 − b \cdot 1 + 1 \\ &= 2 + a − b + 1 \\ &= a − b + 3 \end{align}\)
より、
\(a − b + 3 = 3\)
\(a − b = 0\) …①
また、
\(\begin{align} P(−1) &= 2(−1)^3 + a(−1)^2 − b(−1) + 1 \\ &= −2 + a + b + 1 \\ &= a + b − 1 \end{align}\)
より、
\(a + b − 1 = 5\)
\(a + b = 6\) …②
得られた関係式を連立し、定数 \(a\), \(b\) を求めます。
① + ②より、
\(\begin{array}{rr} a − b =& 0\\ +) a + b =& 6 \\ \hline 2a =& 6 \end{array}\)
よって
\(a = 3\) …③
③を①に代入すると、
\(3 − b = 0\)
\(b = 3\)
答え: \(a = 3, b = 3\)
\(P(x) = 2x^3 + ax^2 − bx + 1\) において、剰余の定理より
\(P(1) = 3\), \(P(−1) = 5\)
\(\begin{align} P(1) &= 2 \cdot 1^3 + a \cdot 1^2 − b \cdot 1 + 1 \\ &= 2 + a − b + 1 \\ &= a − b + 3 \end{align}\)
より、
\(a − b + 3 = 3\)
\(a − b = 0\) …①
また、
\(\begin{align} P(−1) &= 2(−1)^3 + a(−1)^2 − b(−1) + 1 \\ &= −2 + a + b + 1 \\ &= a + b − 1 \end{align}\)
より、
\(a + b − 1 = 5\)
\(a + b = 6\) …②
① + ②より、
\(\begin{array}{rr} a − b =& 0\\ +) a + b =& 6 \\ \hline 2a =& 6 \end{array}\)
よって
\(a = 3\) …③
③を①に代入すると、
\(3 − b = 0\)
\(b = 3\)
答え: \(a = 3, b = 3\)
上記例題①、②は剰余の定理を使う基本的な問題なので、しっかり理解しておきましょう。
剰余の定理の応用問題
最後に、剰余の定理の応用問題にチャレンジしてみましょう。
応用問題①「二次式で割った余りを求める」
整式 \(P(x)\) を \((x + 5)\) で割ると余りは \(8\)、\((x − 2)\) で割ると余りは \(4\) となる。
このとき、\(P(x)\) を \(x^2 + 3x − 10\) で割ったときの余りを求めなさい。
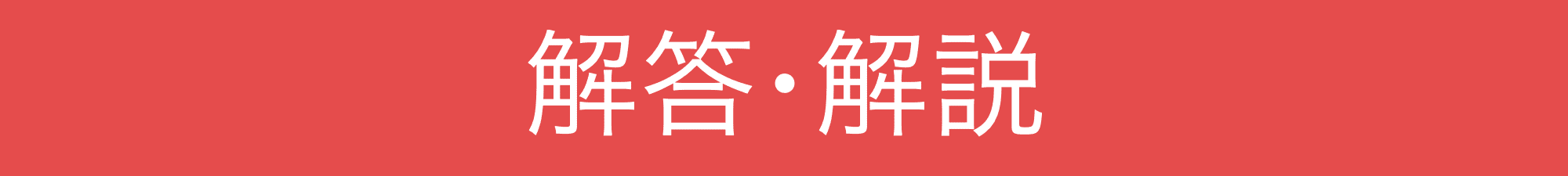
整式を二次式で割った余りは一次式以下になるので、\((ax + b)\) とおけます。
また、\(x^2 + 3x − 10\) と \((x + 5)\)、\((x − 2)\) の関係に気づけると、条件式が \(2\) つ作れます。
\(x^2 + 3x − 10 = (x + 5)(x − 2)\)
\(P(x)\) を \(x^2 + 3x − 10\) で割ったときの商を \(Q(x)\)、余りを \(ax + b\) とすると、
\(P(x) = (x + 5)(x − 2) Q(x) + ax + b\)
と表せる。
整式 \(P(x)\) において、剰余の定理より
\(P(−5) = 8\)、すなわち
\(−5a + b = 8\) …①
\(P(2) = 4\)、すなわち
\(2a + b = 4\) …②
① − ② より、
\(\begin{array}{rr}−5a + b =& 8 \\ −) 2a + b =& 4 \\ \hline −7a =& 4 \end{array}\)
よって
\(\displaystyle a = −\frac{4}{7}\) …③
③を②に代入すると、
\(\begin{align} b &= 4 − 2 \left( −\frac{4}{7} \right) \\ &= \frac{28 + 8}{7} \\ &= \frac{36}{7} \end{align}\)
したがって、
\(\begin{align} ax + b &= −\frac{4}{7} x + \frac{36}{7} \\ &= −\frac{4}{7} (x − 9) \end{align}\)
答え: \(\displaystyle −\frac{4}{7} (x − 9)\)
応用問題②「重解をもつ商で割った余りを求める」
\(P(x) = x^8\) を \((x + 2)^2\) で割ったときの余りを求めなさい。
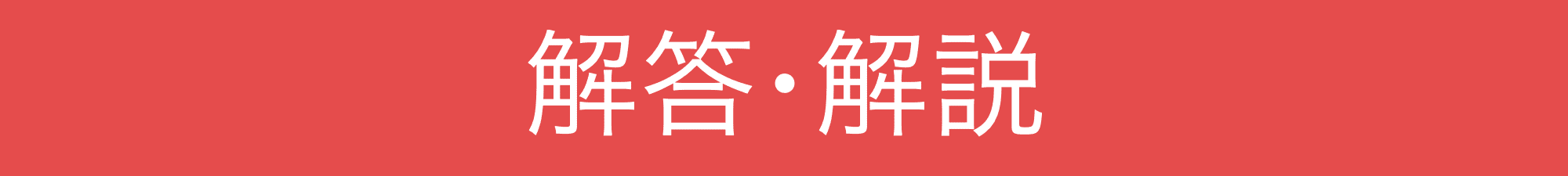
\((x + 2)^2\) のように重解をもつ項で整式を割ると、条件式が \(1\) つしかなく、情報が足りません。
そのような場合は、両辺を微分して条件式を増やします。
この問題には数IIIの微分の知識が必要なので、まだ習っていない人はスキップしてください。
ちなみに、積の微分公式 \(\{f(x)g(x)\}’ = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\) を利用します。
\(x^8\) を \((x + 2)^2\) で割ったときの商を \(Q(x)\)、余りを \(ax + b\) とすると、
\(x^8 = (x + 2)^2 Q(x) + ax + b\) …①
と表せる。
①の両辺に \(x = −2\) を代入すると、
\(256 = −2a + b\)
\(−2a + b = 256\) …①
また、①の両辺を微分すると
\(8x^7 = 2(x + 2) Q(x) + (x + 2)^2 Q’(x) + a\)
\(x = −2\) を代入すると、
\(8(− 2)^7 = a\)
\(a = −1024\)
①より
\(\begin{align} b &= 256 + 2a \\ &= 256 + 2(−1024) \\ &= −1792 \end{align}\)
よって求める余りは \(−1024x − 1792\)
答え: \(−1024x − 1792\)
以上で問題も終わりです!
剰余の定理について理解が深まりましたか?
問題のパターンはある程度決まっているので、たくさん問題を解いて解き方をマスターしましょう!

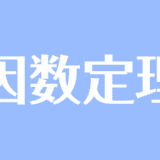

応用問題②についてですが、微分するところで(x^8)’=8x^7となるので答えは-1024x-1792となるように思ったのですが如何でしょう。
この度はコメントいただきありがとうございます。
該当部分を修正いたしました。
チェックが行き届いておらずお恥ずかしいかぎりです。
このようにご指摘いただけるととても助かります。
今後ともどうぞ当サイトをよろしくお願いいたします。